インターフフェイス懐疑論者ヒロアキ
どうも、ヒロアキです。インターフェイス理論懐疑論者です。
Interface 理論とは何か。実は、僕自身良く分かっていません。
ただし、インターフェイス研究をしている人が書いた論文や著作を、いくつか読んだことはありました。
おそらく、日本のネットユーザーに一番認知されているインターフェイス論者は、ゆ〇言語学外注ラジオに登場した Shimomura Koji という人でしょう。
因みに、Shimomura 氏の博論は、無料で閲覧できます。(以下のリンクを参照)
“The Theory of Quotative Complementation in Japanese Semanticosyntax” by Koji Shimamura (uconn.edu)
実は、僕はこの論文を半年くらい前に印刷して、手元に持っています。
しかし、読破するには至っていません。2~30ページ読んだところで、挫折してしまいました。
確か、これを読み始めた瞬間に、「インターフェイスじゃんか」と気づいて、読むのをやめてしまったのです。
今もそうですが、当時の僕は Interface 論に対しかなり懐疑的でした。
インターフェイスを扱った論文は、every, all, some, 等の quantifier (数量詞)と呼ばれるものを、ほぼ確実に扱います。
また、not 等、否定の scope (作用域)というものも扱うことが多いようです。
文によっては、こうした数量詞や否定の解釈が曖昧なのだそうです。要するに、every や all 等の数量詞に関して何通りもの解釈ができる文が存在するそうです。
そうした曖昧性はどこから来来るのか。こうしたことを理詰めで考えるのが、インターフェイス研究家なのだそうです。
例えば、こうした曖昧性を持つ文として、Reinhart (2006) は以下を提示しています。
a. Two flags are hanging in front of three buildings. (Rainhart 2006: 117)
この文は二通りの解釈ができるそうです。
一つ目の解釈では、3つの建物全体の前に旗が2本立っているので、旗は合計で2本だけです。
二つ目の解釈では、建物1件につき2本の旗が立っているので、合計の旗の本数は6本です。
こうした曖昧性を説明するために、インターフェイス研究科は様々な手法を使ってきました。
scope shift (数量詞の作用域がシフトする)とか、Qunatifier Raising (数量詞が非顕在的ないどうをする)等がその典型例でしょう。
非顕在的な移動というのは、目に見えない移動ということです。言語は音声なので、「語順の変化に現れない移動」とか、「音声に影響を与えない移動」と言った方がより適切なのかも知れません。
こうした「語順の変化に現れない」移動は、どうやって起こっているのでしょうか。実のところ、この分野の専門家ではない僕には良く分かりません。
生成文法では、要素を組んで文を作る統語の部門と、意味理解をする部門を分けて考えています。それぞれ、Narrow Syntax と Concept Interpretation (C-I) Interface と呼ばれています。
Interface 研究家が多用する目に見えない移動は、おそらく意味理解を司る C-I interface で起こっていると考えられているのではないでしょうか。
だからこそ Interface 研究という名前がついているのでしょう。
もしくは、統語を司る Narrow Syntax で本当にそういう移動現象が起こって、それが Spell-Out (発音)されないという考え方かもしれません。
ともかく、僕はこの分野の専門家ではないので、あまりはっきりしたことは言えません。
ただ、Qunatifier Raising 等の「目に見えない要素の移動」があるということは知っていました。
ただし、こうしたアプローチに対し、僕はかなり懐疑的でした。
なぜなら、そんな「目に見えない移動」等を持ち出し始めると、本当になんでも「説明」できてしまうからです。
さらに、Interface 研究家がよく使う論理表示が難しかったのも良くなかったようです。E とか、A の逆記号とかです。
こうした論理表示をきちんと読めないと Interface 研究家が書く論文は読めません。
そして、昔の僕はこれが読めませんでした。
その結果、Interface が分からなくなる ⇒ ますます懐疑的になる ⇒もっと Interface を避ける ⇒ もっと分からなくなる。
こういう流れが完成していました。
ただし、Chomsky (2021a) では、interface level を想定しないという提案がなされています。よって、Interface をあまりやらないという選択肢もありのようです。
インターフェイス研究始めました
時は流れ、自分の研究分野も少しずつ変化していきました。
僕の研究は、関係代名詞から始まりました。Radford (2016, 2019) で紹介されている Antecedent Raising という操作に異議を唱えることを目標としていました。
しかし、研究を進めていく中で、himself や each other 等の anaphor と呼ばれる物を詳しく調べる必要があることが分かってきました。
そして、Chomsky (2021a) によると、Reuland という人が書いた Anaphor and language design という本が、この分野における必読書なのだそうです。
もちろん、Reuland の本を読みました。そして、以下の2つのことを思いました。
① 理解するには Interface 論が必要。
② Reuland は、Tanya Reinhart という人の著作に大きな影響を受けている。
そして、Tanya Reinhart は Interface 論をたびたび使うことも判明しました。
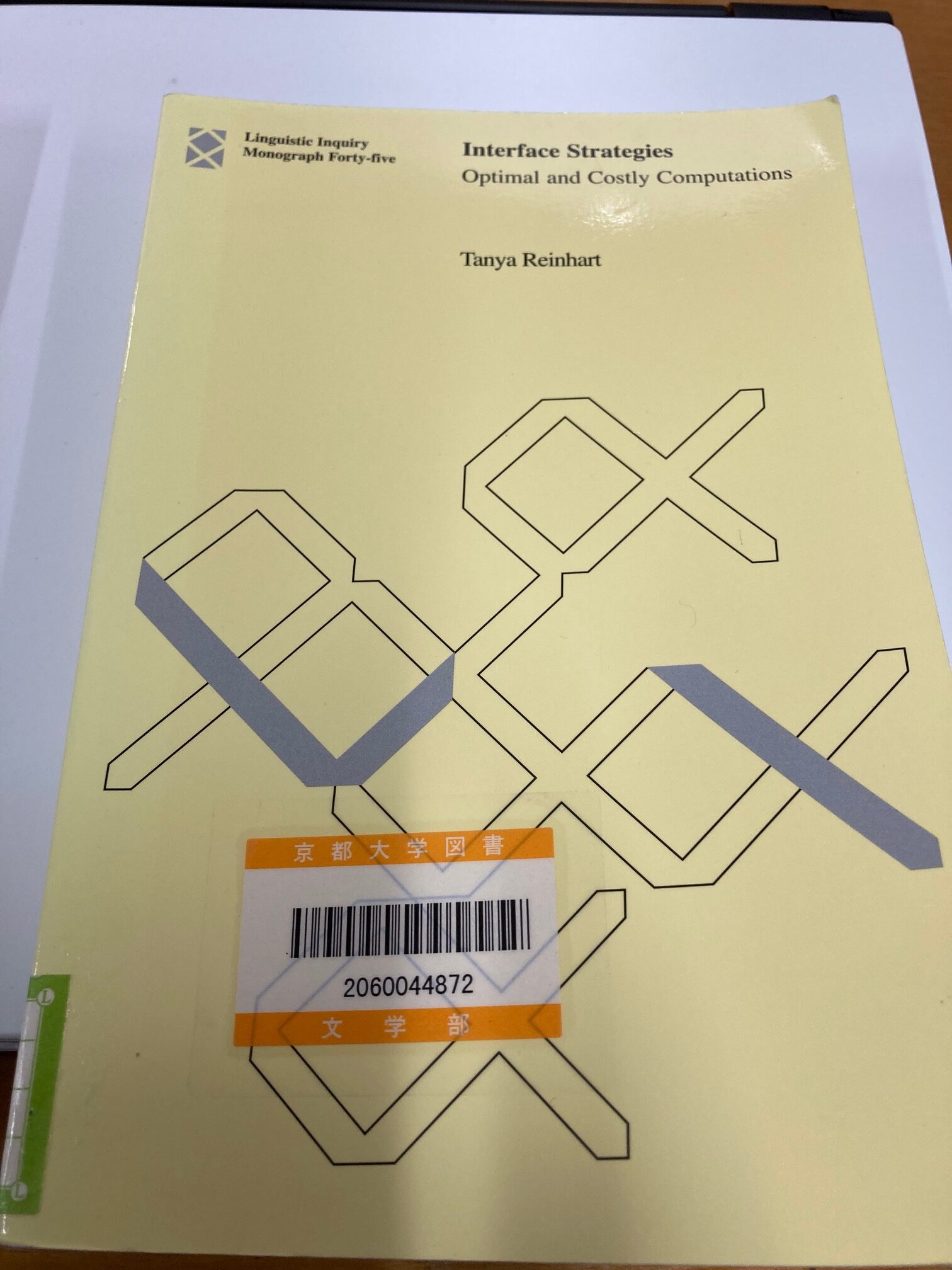
Rainhart, Tanya (2006) Interface Strategies: Optimal and Costly Computations. Cambridge, MA: MIT Press.
上は、Reinhart の代表作です。やはり Interface 論を多用しています。
かなり前から思っていたことですが、生成文法家を志すのなら、どうやら生成文法の全分野をやる必要があるようです。
以前、理学部数学家の学生と話したことがあるのですが、数学でも同じことが言えるらしいです。
彼曰く「数学は全単元全範囲やってないと論文は書けない」らしいです。
生成文法も多分同じです。ただ、理学部数学家の学生と僕が違う点は、僕は空きコマ生成文法家だという点です。
僕の場合、生成文法は全て空きコマで、自学自習でやります。
以前は、読まなければならない著作の量(1000点くらい?)や、自力で理解しなければならないことの多さに、弱音を吐いていたこともあります。
今も結構弱音を吐きます。
しかし、今は昔に比べて実力がついてきたので、「まあ、できるんじゃない?」と思うことが多くなりました。
Interface 理論も、最初の内は、λ function 等が分からずに、「敷居の高さ」みたいなものを感じてしまいました。
しかし、人間というのは不思議な生き物で、ある程度こういう物を見続けると、だんだん慣れてきます。
